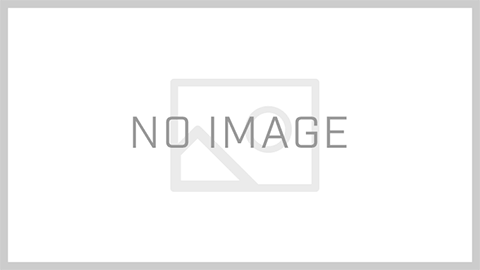2022年2月7日、北京冬季オリンピック。
スキージャンプ混合団体という新種目で、高梨沙羅選手が103メートルの大ジャンプを決めた瞬間、日本中が歓喜に沸いた場面を、今でも鮮明に覚えている方も多いのではないでしょうか。
ところが、その記録はあっけなく「無効」となり、高梨選手は雪上で泣き崩れることになります。
理由は「スーツ規定違反」。
正直、このニュースを聞いたとき、私も「スーツの規定ってそんなに厳しいの?」と驚きました。
スキージャンプを見るのは好きだけれど、選手が着ているあのピチピチのスーツに、そこまで厳格なルールがあるとは知らなかったからです。
しかも「たった2センチ」の差で失格になったという。
2センチといえば、親指の幅ほど。
日常では気にも留めない小さな差です。
そんな微々たる差が、オリンピックのメダルを左右するなんて、素人には理解しがたい世界ではないでしょうか。
今回は、あの日何が起きたのか、なぜ2センチがそこまで重大な問題になったのか、そして極寒の会場が高梨選手の体にどんな影響を与えたのか、できるだけわかりやすく、でも心に寄り添うように紐解いていきます。
高梨沙羅が北京五輪で失格した理由は!
あの日の北京で起きた出来事は、単なる「ルール違反」では片付けられない、選手の無念さがにじむ複雑さを持っています。
スキージャンプという競技の特殊性、そしてスーツをめぐる各国の攻防を知ると、高梨選手が置かれた状況がいかに厳しいものだったかが見えてきます。
まず、スキージャンプのスーツに関するルールを確認しておきましょう。
国際スキー・スノーボード連盟(FIS)は、競技の公平性を保つため、スーツのサイズに非常に細かい規定を設けています。
基本的な考え方は「スーツは選手の体にぴったり密着していなければならない」というもの。
なぜかというと、スーツが体から離れてゆとりがあると、空中で空気を溜め込み、いわば「帆」のような役割を果たしてしまうからなのです。
1990年代から2000年代初頭にかけて、スキージャンプ界では「むささびスーツ」と呼ばれる、ダボダボのスーツが横行していた時期がありました。
脇の下から腰にかけて布を大きく張り出させ、文字通りムササビのように滑空距離を稼ぐ手法です。
当然ながら、これでは純粋な技術勝負とは言えなくなってしまう。
そこでFISは段階的にルールを厳格化し、現在のような「体に密着」が基本となるスーツ規定が生まれたわけです。
女子選手の場合、体のサイズに対してスーツが許容されるプラス分は、部位によって異なりますが、多くの箇所で2センチから4センチ(最大4センチ)と定められています。
太もも部分の場合、体から最大4センチまでのゆとりが許される中で、高梨選手は2センチオーバーしたと判定されたのです。
「2センチオーバーなら、最大6センチ?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、ルールはあくまで「上限」を定めているのであって、その上限を1センチでも超えれば違反は違反。
交通違反と同じで、制限速度50キロの道路を52キロで走っても「たった2キロオーバー」とは言い訳の余地がないのと同じ厳しさです。
当日の混合団体では、高梨選手は1回目に103.0メートルという素晴らしい飛距離を記録しました。
124.5点という高得点で、チームは暫定で好位置につけていたはずです。
ところが、飛躍後に行われるランダム検査に引っかかってしまった。
この検査は全選手に対して行われるわけではなく、無作為に抽出された選手だけが対象となる、いわば「抜き打ちテスト」のようなもの。
高梨選手はまさかの抽出に当たり、そして違反が発覚してしまったのです。
失格を告げられた高梨選手は、ランディングゾーンで崩れ落ち、スタッフに抱えられるようにしてその場を離れました。
後に彼女はSNSで長文の謝罪を投稿し、「私の失格のせいで皆のメダルのチャンスを奪ってしまった」「関わる皆さんの人生を変えてしまった」という言葉で自身を責めています。
あの黒い背景に白い文字だけが浮かぶ投稿画面を見たとき、胸が締め付けられる思いをしたのは、私だけではないはずです。
ただ、この日失格になったのは高梨選手だけではありませんでした。
ドイツ、オーストリア、ノルウェーの女子選手も次々と同様の理由で失格となり、計5人(日本、ドイツ、オーストリア、ノルウェーから)の女子選手が記録を取り消されるという異常事態が発生したのです。
ドイツのカタリナ・アルトハウス選手は涙ながらに「FISが女子ジャンプを壊した」と訴え、各国の監督たちも「検査方法が変わったのではないか」「理解できない」と抗議の声を上げました。
一方、FIS側の検査官は「今年はスーツが本当にひどく大きかった。だから厳しく対応した」と説明しています。
つまり、各国が「ギリギリを攻める」開発競争を繰り広げた結果、検査する側も締め付けを強化したという構図が見えてきます。
スキージャンプのスーツ開発は、各国がしのぎを削る技術戦争の側面もあり、数ミリ単位でルールの隙間を突こうとする攻防が日常的に行われているのが現実なのです。
結局、日本チームは4位でメダルに届きませんでした。
高梨選手は別のスーツに着替えて2回目のジャンプに臨み、98.5メートルを飛びましたが、1回目の失格が大きく響いた形です。
あと少しで表彰台に届いたかもしれないという悔しさは、本人はもちろん、応援していたすべての人の心に深く刻まれたことでしょう。
高梨沙羅のスーツ規定違反は太もも2cm?
では、具体的に高梨選手のスーツのどこがどう問題だったのか、もう少し詳しく見ていきましょう。
「たった2センチ」という数字が持つ意味と、スキージャンプにおけるスーツの重要性を理解すると、この問題の本質が見えてきます。
日本チームのコーチ陣、横川朝治ヘッドコーチや鷲澤徹コーチの説明によると、検査で指摘されたのは「太もも周り」の部分でした。
両方の太もも部分が、規定より約2センチ大きかった(オーバー)ということです。
コーチ陣は「全く本人のせいではない」「スタッフの確認不足だった」と高梨選手をかばうコメントを出していますが、結果として違反は違反。
競技の世界では、理由がどうあれルールを超えたら失格という厳しい現実があります。
さて、ここで素朴な疑問が浮かびます。
スーツが2センチ大きいだけで、そんなに飛距離が変わるものなのでしょうか。
実は、スキージャンプの世界では驚くほど変わるのです。
一部の試算によると、スーツの表面積がわずか1センチ増えるだけで、飛距離が約2.8メートル伸びるという計算があります。
つまり、2センチ大きければ理論上は5メートル以上のアドバンテージが得られる計算になる。
オリンピックや世界選手権では、0.5メートル差でメダルの色が変わることも珍しくありません。
そう考えると、2センチという数字がいかに重大な意味を持つかがわかってきます。
スキージャンプという競技は、もともと体重が軽いほど有利という特性を持っています。
軽ければ軽いほど空中で浮きやすく、より遠くまで飛べる。
この理屈から、かつては選手たちの間で過激な減量競争が横行し、摂食障害を発症する選手も少なくありませんでした。
特に1990年代後半から2000年代にかけては深刻な問題となり、痩せすぎて競技を続けられなくなった選手、健康を害して引退に追い込まれた選手も存在しています。
この状況を改善するため、FISは選手のBMI(体格指数)に基づいてスキー板の長さを制限するルールを導入しました。
痩せすぎている選手は短いスキー板しか使えなくなるため、不当なアドバンテージが得られなくなる仕組み。
同時に、スーツに関しても厳格な規定が設けられ、「体に密着」という原則が徹底されるようになりました。
つまり、スーツ規定の厳しさは、選手の健康を守るためという側面も持っているのです。
もしスーツを自由にできるなら、各国は競って浮力を稼げるスーツを開発するでしょう。
そうなれば、また体重を極限まで落として少しでも浮きやすくしようという選手が出てきかねない。
スーツ規定は、そうした負のスパイラルに歯止めをかける役割も担っているわけです。
とはいえ、各国の開発競争は止まりません。
ルールの範囲内で、いかにギリギリまで浮力を稼ぐか。
その攻防は熾烈を極めており、検査する側と開発する側の「いたちごっこ」が続いています。
高梨選手のケースも、決して「ずるをしようとした」わけではなく、この開発競争の中で生じた不幸な出来事だったと考えるのが自然でしょう。
コーチ陣の言葉を借りれば、「スタッフの確認不足」ということになりますが、これは誰か一人を責めるべきものではなく、チーム全体で背負うべき問題だったのかもしれません。
スキージャンプのスーツは、選手一人ひとりの体型に合わせてオーダーメイドで作られ、試合ごとに細かく調整されます。
体重が数百グラム変わっただけでもフィット感が変化するほど繊細なもので、完璧な管理を維持するのは至難の業なのです。
興味深いのは、高梨選手がこの日問題になったスーツを、2日前の個人戦(ノーマルヒル)でも着用していたという事実です。
そのときは何の問題もなく検査をパスしている。
同じスーツなのに、なぜ2日後には違反になったのか。
この謎を解く鍵が、次に述べる「極寒」の影響にあるのではないかと考えられています。
高梨沙羅が失格した当日の極寒の影響は!
北京冬季オリンピックのスキージャンプ会場は、河北省張家口にある国家ジャンプセンターでした。
この会場が、実に過酷な環境だったことをご存知でしょうか。
当日の気温は氷点下15度を下回り、風を考慮した体感温度はマイナス30度近くまで下がったという報告もあります。
連日、夜間にはマイナス20度に迫る冷え込みが続き、選手たちは文字通り「凍える」ような条件の中で競技に挑んでいたのです。
この極寒が、高梨選手の体にどのような影響を与えたのか。
コーチ陣や専門家の分析によると、寒さと標高の高さ(会場は約1600メートル以上の高地)が複合的に作用し、選手の体型にわずかな変化をもたらした可能性が指摘されています。
まず、脱水の問題があります。
極度に寒い環境では、人間の体は思っている以上に水分を失います。
呼吸のたびに水蒸気として水分が出ていき、汗をかいている実感がなくても体内の水分量は減少していく。
特に標高の高い場所では、乾燥した空気によってこの傾向が強まります。
高梨選手のようにトップアスリートは、総じて体脂肪率が非常に低いという特徴があります。
体脂肪率が低いということは、体内に水分を保持しにくいということでもある。
ちょっとした環境の変化で水分が抜けやすく、それによって体のサイズも微妙に変動するのです。
コーチの説明によれば、寒さの中では筋肉が十分に膨らまず、力を入れにくい状態になるといいます。
通常、筋肉は運動すると血流が増えて一時的に膨張する、いわゆる「パンプアップ」状態になりますが、極寒の環境ではこの反応が鈍くなる。
結果として、太もも周りのサイズが通常よりも小さくなり、相対的にスーツが「ゆるく」見えてしまう可能性があるわけです。
2日前の個人戦では問題なかったスーツが、混合団体で失格になった理由。
それは、選手がサボったわけでも、スタッフが油断したわけでもなく、気温や標高、そして選手の体調という不可抗力的な要素が絡み合った結果だったのかもしれません。
また、北京五輪はコロナ禍での開催という特殊な事情もありました。
選手たちは厳格な隔離生活を送りながら競技に参加しており、食事や体調管理に制約があったことは想像に難くありません。
普段通りのコンディションを維持すること自体が難しい状況だったはずです。
各国の選手や監督からも同様の声が上がっていました。
「隔離中の生活で体調管理が難しかった」「普段と同じようにはいかなかった」という証言は、高梨選手だけでなく多くのアスリートに共通する悩みだったようです。
結局のところ、FIS側は「ルール通りに検査しただけ」という姿勢を崩さず、選手側は「厳しすぎる」と訴えるという対立構造のまま、この問題は幕を閉じました。
どちらの言い分にも一理あり、白黒つけることは難しいのが正直なところです。
ただ、一つだけ言えるのは、高梨選手は意図的に不正を働いたわけではないということ。
むしろ、彼女は長年にわたって日本のスキージャンプ界を牽引し、女子ジャンプの発展に多大な貢献をしてきた選手です。
そんな彼女が、オリンピックという最高の舞台で、自らの意思とは無関係な理由で失格の烙印を押されてしまった。
その無念さは、想像するだけでも胸が苦しくなります。
あの日、黒い画面に白い文字だけを載せて謝罪の言葉を綴った高梨選手。
「日本代表として夢のメダルを獲得できるチャンスだったのに、私の失格のせいでみんなの夢を奪ってしまった」という一節は、読む者の心を打ちました。
しかし、本来責められるべきは高梨選手ではなく、数センチの誤差で選手の夢を砕いてしまう規定の運用方法、あるいはそうした事態を招いた開発競争の過熱ぶりなのかもしれません。
嬉しいことに、高梨選手は失意のどん底から立ち上がりました。
一時は引退も考え、自宅にこもるほど落ち込んでいたといいますが、ファンからの励ましの声やチームメイトの支えによって再び飛ぶことを決意。
2026年のミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、混合団体で銅メダルを獲得し、4年前の「悔し涙」を「嬉し涙」に変えてみせました。
あの北京での出来事は、高梨選手にとって忘れたい過去であると同時に、乗り越えたからこそ手に入れた強さの源でもあるのでしょう。
スキージャンプという競技の厳しさ、そしてそれを超えていく選手の精神力。
2センチという小さな数字が引き起こした大きなドラマは、スポーツの残酷さと美しさを同時に見せてくれました。
高梨沙羅選手のこれからの活躍に、引き続き注目していきたいと思います。