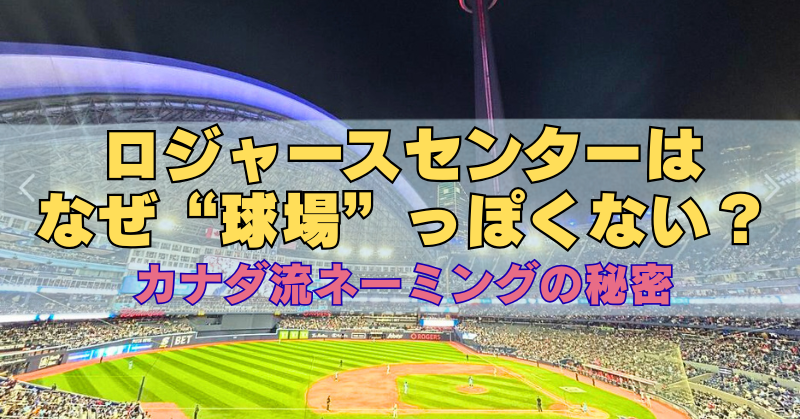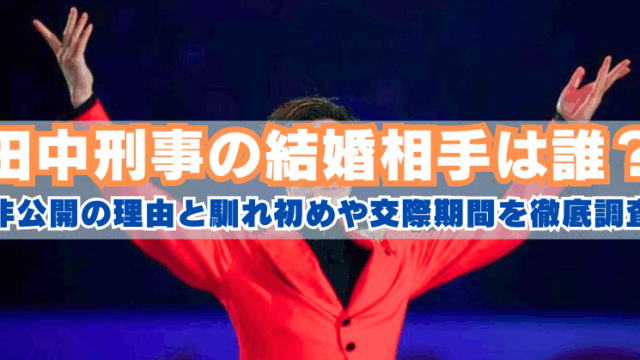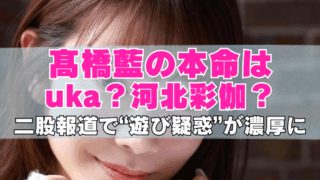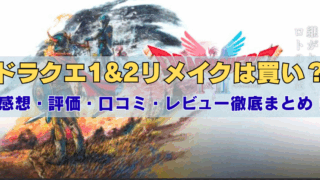「ロジャースセンター」って、なんか野球場っぽくない…そう感じたことはありませんか?
実はその名前、ただのセンスじゃなく“とある理由”がちゃんとあるんです。
アメリカやカナダの球場名には、ある共通点があって――
この記事では、その“違和感”の正体をゆるっと解き明かしていきます。

なぜ“球場”っぽくない?その違和感の正体
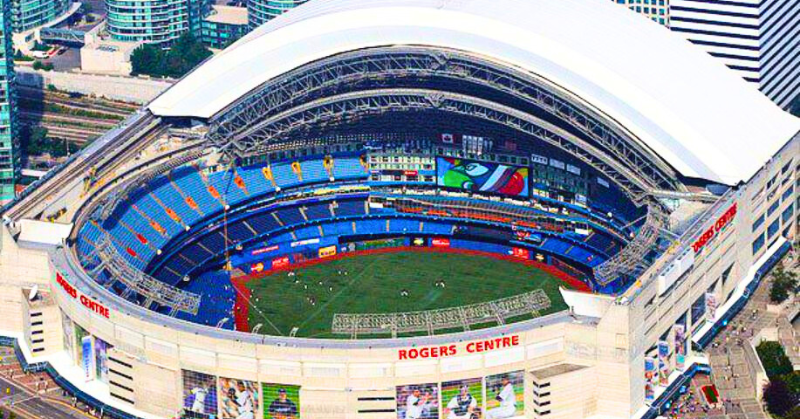
引用元:@ballpark_bot
「ロジャースセンター」って聞いて、「ん?これってホントに野球場?」って思ったことありませんか?
なんか…ちょっとオシャレすぎるというか、ショッピングモールかカンファレンス会場みたいな名前。
どうにも“野球っぽさ”が伝わってこないんですよね。
日本の野球場って、「東京ドーム」とか「阪神甲子園球場(こうしえんきゅうじょう)」とか、聞いた瞬間に「あ、野球やってるとこだな」って分かる名前が多いです。
でもロジャースセンターは…どうしてこうなった?
この“違和感”の正体、それはズバリ「名前を企業がお金でつけているから」です。
ちょっとビックリするかもしれませんが、これって北米ではすごくフツウのこと。
「ネーミングライツ(命名権)」っていう仕組みがあって、企業がお金を出して施設の名前を決めることができるんです。
ロジャースセンターも、もともとは「スカイドーム」って名前で1989年に開場しました。
でも、2005年にカナダの大手通信会社「ロジャース・コミュニケーションズ」が命名権を取得して、自社の名前をつけたんです。
それが今の「ロジャース・センター」というわけ。
とはいえ、ここでまたひとつ疑問が出てきますよね。
「じゃあ、“ロジャース・スタジアム”じゃダメだったの?」って。
そう、そこなんです。
「センター」というちょっと不思議な名前にも、ちゃんと理由があるんです。
次のセクションでは、その“センター”にこめられた意味を見ていきましょう。
ロジャースセンターの名前の意味とは
さて、「ロジャースセンター」って名前、なんで“スタジアム”じゃないの?って、ちょっと気になりますよね。
日本の野球場だったら、「東京ドーム」とか「阪神甲子園球場(こうしえんきゅうじょう)」みたいに、聞いただけで「野球の場所だな」ってすぐ分かるのが普通です。
でも、「センター」って聞くと、なんだか野球場っぽくない。
まるで展示会場とか、ショッピングモールみたいな響き。
でもこれ、ちゃんと理由があるんです。
実はロジャースセンター、野球だけをする場所じゃないんですよ。
いろんなイベントに対応できる“多目的(たもくてき)施設”なんです。
たとえば、かつてはカナダのバスケットボールチーム「トロント・ラプターズ」の本拠地としても使われていました。
そして、過去にはアメフトの試合――バッファロー・ビルズのプレシーズンゲームなんかも開催されたことがあります。
つまり、「野球専用の場所」じゃないんですね。
だから“スタジアム”というより、もっと広い意味で使える“センター”という名前が選ばれたわけです。
ちょっとイメージしてみてください。
定食屋よりもフードコート、映画館よりもショッピングセンター。
なんでもそろってて、いろんな人が集まる“中心”の場所。
そういう場所に「センター」って言葉、なんだかしっくりきませんか?
ちなみにロジャースセンターには開閉式の屋根がついていて、雨でも雪でもイベントOK。
中はめちゃくちゃ広くて、野球だけじゃもったいないくらい。
コンサート、展示会、大会…なんでもこなせる“イベントの万能選手”なんです。
だから、「ロジャース・スタジアム」ではなく、「ロジャース・センター」。
名前の響きがちょっと地味に感じるかもしれませんが、そこにはちゃんと意味がこめられていたんですね。
そしてこの“センター”という名前の使い方、実はロジャースセンターだけの話じゃないんです。
アメリカでもよく見かけるんですよ。
次のパートでは、そのへんをもう少し深掘りしてみましょう。
アメリカ球場名の傾向とカナダ流の違い
ここまで読んで、「ロジャースセンターって、ちょっと特殊なパターンなのかな?」と思った方もいるかもしれません。
でも実は、アメリカでも“センター”とか“アリーナ”ってつく名前、けっこう見かけるんです。
その理由はシンプル。
北米では球場やアリーナの名前に企業名を入れるのがごくふつうのことなんです。
たとえば、ロサンゼルスにある「クリプトドットコム・アリーナ」。
ここはレイカーズやクリッパーズが試合をする超有名な場所ですが、以前は「ステープルズ・センター」って名前でした。
この“ステープルズ”は文房具の会社。つまり、命名権を持っていたってことなんです。
他にも、「キャピタル・ワン・アリーナ」(ワシントンD.C.)や、「ステートファーム・アリーナ」(アトランタ)など、
企業名+アリーナやセンターの組み合わせはアメリカ全土で広く見られます。
一方で、野球専用の球場には「スタジアム」や「フィールド」といった名前が多く見られます。
たとえば、
・ヤンキー・スタジアム(ヤンキース)
・ドジャー・スタジアム(ドジャース)
・ブッシュ・スタジアム(カージナルス)
こうした球場は、観客席やフェンスの高さなど、すべてが“野球のため”に設計された場所。
だからこそ「スタジアム」という名前がしっくりくるんですね。
じゃあ「センター」や「アリーナ」って何がちがうの?というと、これは“多目的型”であることがポイントです。
つまり、野球だけじゃなくて、バスケ、コンサート、展示会など、なんでもできる会場。
いわば“なんでも屋さん”の会場には、少し広い意味をもつ「センター」や「アリーナ」という言葉が使われやすいんです。
そして、こうした施設の多くがネーミングライツによって企業名を冠しているのが特徴。
「球場=広告の顔」という感覚。企業にとってはブランド力アップ、球場にとってはお金が入って助かる。
まさにおたがいメリットがある関係なんです。
日本でも「ベルーナドーム」や「エスコンフィールドHOKKAIDO」など、少しずつ企業名を取り入れた施設が出てきています。
ですが、まだまだ“名前を売る”ことに抵抗を感じる人も多いのが現状。
でも、こうやって比べてみると、「ロジャースセンター」って実はすごく“北米らしい名前”なんですよね。
ただの野球場じゃない、多目的で、企業名もしっかり前に出すスタイル。
名前の違いには、その国の価値観や考え方がにじみ出ているのかもしれません。